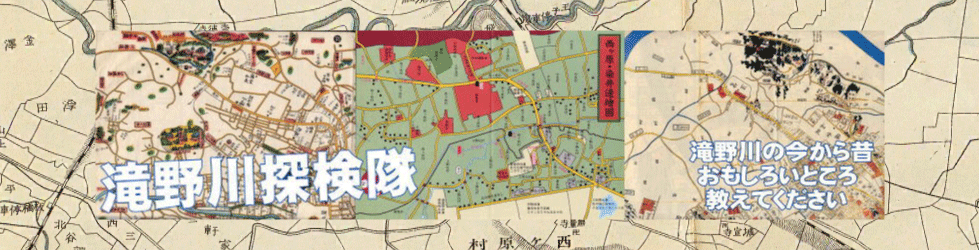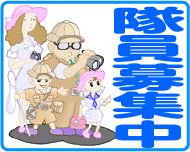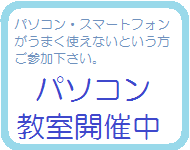滝野川界隈のむかし・いま・みらい
大正12(1923)年9月1日
記述された関東大震災
滝野川界隈の関東大震災がいかなるものであったか、残されている文章から抜粋をしてみる。
まず、公式記録ともいうべき「滝野川町誌」(昭和6年刊)では、
この日、東京では前夜來多少の風雨が断続的にあつたが、氣温は平年よりも高くて、盛夏の如き暑さを感ずる程で、何となく息苦しさこそ感じたが、地震なぞとは夢にも想像しなかりた。斯くして牛前十一時五十八分四十四秒、俄然、関東一帯は轟然たる地鳴りと共に、振幅四寸といふ大地震は襲来したのであつた。次で午後零時四十分、強度の余震が襲来し、一層被害を大にして、正に安政以来の激震というふことであった。
この實に強烈な振動に、東京府に於ける家屋の倒壊せるもの算なく、殊に近代科學の産物として建設された、所謂鉄筋混凝土の建築物でさへ、見る影もなく裂壊し、飴のやうに捩れ倒れて惨憺たる姿を随所に残した。
而して家屋の倒潰につれ瓦壁飛ひ、砂塵舞ひ、電柱は倒れ、架空線は切断し.當時まで有名であつた、浅草の十二階は首が千切れて飛ぷ騒ぎ、美観を誇つて居た帝都の地は忽ち修羅場と化した。
見るも物凄い入道雲が、彼方の空に立ち現はれ、殺氣は刻一刻と迫る心地がした。到る所、壓死、負傷、親子夫婦兄弟、救ひを求めて相呼び相わめき、 倏ちにして、都下は阿鼻叫喚の巷となり、凄惨そのものゝ天地と變つた。
通信横鱒昧一切停止し、電動力も熄み、唯一の交漁通関である、電車もー切動かず、市内の状勢を知るに由なく、人心は極度に不安に陥り、狼狽と焦慮とで右往左往の人々で混乱する様は筆紙の悉くす所でなかつた。
「滝野川町誌・第一総説・第一章沿革・震災當時の滝野川町・安政以來の激震」 より
関東大震災後の1926年(大正15年・昭和元年)1月、22歳で駒込神明町に住むことになる佐多稲子は、日本橋の丸善書店洋品部の女店員として震災を経験している。
ガラス窓のある鉄筋コンクリートの建物が大きく震れるとき、ガチャーン、ガチャーン、と瀬戸物を入れた籠か、ピール壜をいっぱい詰めた箱でも揺すぶるような音がした。丁度食事どきで、店員たちの半分は食堂へ行っていたし、客の姿も少くて、店は閑散としていた。私は女店員のひとりと抱き合って店の中ほどの飾りケースのそばに揺すられるままになつていたが、奥の高い帽子棚から白い帽子の箱が放り出すように、ぽんぽんと落ちていた。香水の棚から転り落ちる香水の積は、まるで小鳥の群が枝から枝へ飛び移るような可憐さで私の視野を横切る。はっと身体の痛むおもいで、石畳の上に叩きつけられる香水の埠をおもった。飾りケースの上に立ててあったネクタイ掛けが横倒しになり、その向うを、背を丸くして泳ぐように外へ飛び出してゆく人の姿が見えた。大きな建物ごと、ガチャーン、ガチャーンと揺すられるたびに、私は自分を、大きな箱の中に入れられた玩具のひとつのように感じた。だがその箱の周囲は広くて、高くて、箱そのものがいつもの高い天井よりもずうっと恐ろしかった。
最初の揺れがひと先ず終ったとき、みんな外へ出ろ、と誰かにうながされて、私は抱き合っていた連れといっしょに、入口から外へ出た。出たとたんに、筋向うの野沢組の赤煉瓦の建物が、ざあっと前へ崩れ落ちた。あっ、これが大地震なのだ、と、私はその瞬間にはじめて、今の経験を見定めた。電車通りは、一瞬の夢魔に立ちすくんだ表情から、驚愕へざわめき立つところであった。私たちは真向いの荒囲いの空地へ集まった。食堂へ行っていたものたちが、店の入口から外へ出て来た。私は丸善の入口から人の出て来るのを、今、初めて真向いから眺めた。
日比谷の松本楼から火が出た、とすぐ伝わる。高島屋の前の道路が大きく亀裂して、買物の女が一人落ち込んだ、などとも。店ではすぐそのままおもいおもいの方向に連れを作って帰ることになった。電車は停まってしまっている。私などはいちばん遠い路を歩かねばならなかった。私は少しでも身軽にとおもい、芳子に私の弁当箱をあずけた。そわそわしたおそろしい思いと、これから歩いてゆかねばならぬ覚悟に、私の身体はこまかく慄えている。
「大丈夫? 気をつけてね」
芳子は、私の弁当箱を受けとって、これから歩いてゆく私を見送って、真剣な目になっていた。私は洋書部の女店員のひとりと男店員二人と四人連れで歩き出した。野沢組の赤煉瓦は表どおりへくずれ落ちて、うず高くなつている。私たちがそのそばを通るとき、一人の巡査がその煉瓦の小山の上に乗って手を振っていた。その煉瓦の下に、青バスの車が一台埋まっている、と、大きく書いた板きれを立てていた。洋書部の女店員は、近眼のひどい、色白の穏しい娘であった。南千住から通っているので、ときどき電車で朝夕一緒のことがあった。普段は口数はあまり利かない人だが、あるとき彼女は私を横から見上げるようにして、細い少し鼻にかかる声で、何の前おきもなしに、
「ほんとに、田島さんは、白百合のような方ですわねえ」
と、言ったことがある。この言葉は私を語るよりも、彼女自身を語る言葉である。
顔見知りの若い男店員二人と四人連れは、日本橋の橋を渡って本石町へ出て行ったが、丁度三越の前へ差しかかったとき、にんべんのあった横町通りで、一軒のビルディングの高い窓のひとつひとつから、火焔が外に吹き出していた。高い窓のひとつひとつから放出する火焔が、昼間でもまっ赤に見え、その凄まじさに誰も手をつけようとしていない異常な風景が、おののいた私の心に恐ろしさをそそった。街は誰も声を立てぬままで騒然となっていた。たくさんの人々が歩いてゆく。和泉橋から三筋町の方へ出てゆくと、この辺りでは家の前に家財を運び出した人が、その傍らに坐って、空の煙りを眺めていた。空は地上から湧き起る煙で黒雲を捲き上げていた。厩橋から吾妻橋へかかると、千住の方の空はもうまっ黒で、吾妻橋ぎわはその方から逃げてくる人々で先きへはゆけなくなっていた。
「ええ、もう千住は焼けていますよ」
と、すれ違う男が答えてゆきすぎる。
「私、どうしましょう」
と、千住へ帰る私の連れは泣き出してしまった。吾妻橋の向うの業平も黒煙が捲いている。私はその煙りにさえぎられぬうちに橋を渡ってしまわねばならない。私は三人に別れて、ひとりになり吾妻橋の上を走った。
「私の東京地図」(佐多稲子)
本郷で生まれ育った宮本(中條)百合子(1899〜1951)は、見聞した内容を詳細に書き留めている。建築家であった父中條精一郎(1868~1936)の話として、
その日は一日事務所に行かず。丁度地震の三十分ほど前内外ビルディングに居、人に会うために、ヤマトと云うレストランの地下室で電話帳を見て居た。ところへひどくゆれて来、ガチャガチャ器具のこわれる音がする。父上は、多分客や Waiter があわてて皿や何かをこわしたのだろうと思うと二度目のがかなりつよく来た。これは少しあぶないと、地平ママ室の天井を注目した。クラックが行くと一大事逃げなければならないと思ったのだ。ピリリともしないので、少し落付いたら、食事をする気で居ると、何ともそとのさわぎがひどいので出て見て驚いた。早速、郵船を見ると、どうもガタガタに外がいたんで居るし、内外はピシャンコになって居るし、もう警視庁うらに火が出たし、あぶないと思って、事ム所を裏から大丈夫と知り東京ステーションで Taxi をやとおうとするともう一台もない。しかたがないので、本郷座のよこに来ると今客を降したばかりの白札のに会う。のせろ、いやだめです、かえらなければならない。そう云わずに行けと押問答をして居ると彼方側からも一人駒込に行くからのせろと云う。それでは二人で行きましょうとやっと家にかえった。
かえって見ると、おばあさん二人は竹やぶににげ、英男が土蔵にものを運び込んで、目ぬりまでし、曲って大扉のしまらないのに困って居た。
井戸に、瀬戸ものをつるしまでし。なかなか十五六の男の子としては大出来の功績をあげた。
「大正十二年九月一日よりの東京・横浜間大震火災についての記録-父上の経験」(宮本百合子)
田端在住であった室生犀星(1889~1962)は、震災5日前の8月27日に長女の朝子が生まれている。
地震来る。同時に夢中にて駿臺なる妻子を思ふ。−神明町に出で甥とともに折柄走り来る自動車を停め、團子坂まで行く、非常線ありて己むなく引き返す。とき一時半也。夕方使帰りて妻子の避難先き不明なりと告ぐ。病院は午後三時頃に焼失せるがごとし。或ひは上野の山に避難したるかも知れず、されど産後五日目にては足腰立つまじと思ふ。−−駿臺、廣小路、本郷一丁目総て焼けたりと聞く。されど空しく上野の火をながめるのみ。夜ポプラ倶樂部にて野宿す。一垂なきほどに露にてからだ濡れたり。 上野あたりの煙の鼻に沁みてゑぐさ言はん方なし。家内一同ポプラ倶樂部に避難す。芥川君、渡邉庫輔君を従へて見舞に来る。
「日録 九月一日」 室犀星全集
田端在住であった芥川龍之介(1892〜1927)は震災を田端の自宅で体験している。
午(ひる)ごろ茶の間(ま)にパンと牛乳を喫(きつ)し了(をわ)り、将(まさ)に茶を飲まんとすれば、忽ち大震の来(きた)るあり。母と共に屋外(をくぐわい)に出(い)づ。妻は二階に眠れる多加志(たかし)を救ひに去り、伯母(をば)は又梯子段(はしごだん)のもとに立ちつつ、妻と多加志とを呼んでやまず、既(すで)にして妻と伯母と多加志を抱(いだ)いて屋外に出づれば、更(さら)に又父と比呂志(ひろし)とのあらざるを知る。婢(ひ)しづを、再び屋内(をくない)に入り、 倉皇(さうくわう)比呂志を抱(いだ)いて出づ。父亦(また)庭を回(めぐ)つて出づ。この間(かん)家大いに動き、歩行甚だ自由ならず。 屋(をく)瓦 (ぐわ) の 乱墜(らんつゐ)するもの十余。大震漸く静まれば、風あり、 面(おもて)を吹いて過ぐ。土臭殆( ほとん )ど噎(むせ)ばんと欲す。父と屋(をく)の内外を見れば、被害は屋瓦の墜ちたると石燈籠の倒れたるのみ。
円月堂(ゑんげつだう)、見舞ひに来(きた)る。泰然自若(じじやく)たる如き顔をしてゐれども、多少は驚いたのに違ひなし。病を力(つと)めて円月堂と近鄰(きんりん)に住する諸君を見舞ふ。途上、神明町(しんめいちやう)の 狭斜(けふしや)を過ぐれば、人家の倒壊せるもの数軒を数ふ。また月見橋(つきみばし)のほとりに立ち、遙(はる)かに東京の天を望めば、天、泥土(でいど)の色を帯び、 焔煙(えんえん)の四方に飛騰(ひとう)する見る。帰宅後、電燈の点じ難く、食糧の乏しきを告げんことを惧れ、 蝋燭(ろうそく)米穀 (べいこく)蔬菜(そさい)罐詰(くわんづめ) の類を買ひ集めしむ。
夜(よる)また円月堂の月見橋のほとりに至れば、東京の火災愈(いよいよ)猛に、一望大いなる 熔鉱炉(ようくわうろ)見るが如し。田端(たばた)、日暮里(につぽり)、渡辺町等(わたなべちやうとう)の人人、路上に椅子(いす)を据ゑ畳を敷き、屋外(をくぐわい)に眠らとするもの少からず。帰宅後、大震の再び至らざるべきを説き、家人を皆屋内に眠らしむ。電燈、瓦斯(ガス)共に用をなさず、時に二階の戸を開けば、 天色(てんしよく)常に燃ゆるが如く紅(くれなゐ)なり。
この日、下島(しもじま)先生の夫人、単身(たんしん)大震中の薬局に入り、薬剤の棚の倒れんとするを支(ささ)ふ。為めに出火の患(うれひ)なきを得たり。 胆勇(たんゆう)、僕などの及ぶところにあらず。夫人は澀江抽斎(しぶえちうさい)の夫人いほ女の生れ変りか何かなるべし。
「大正十二年九月一日の大震災に際して 二 大震災日録 九月一日」(底本:「筑摩全集類聚 芥川龍之介全集第四巻」筑摩書房・青空文庫)より
芥川の日記に近隣町の模様も記されているが、渡辺町には野上弥生子がいた。野上弥生子(1885〜1985)は、1906(明治39)年から1917(大正6)年まで、居をかえながらも巣鴨町上駒込に住んでいた。1934(大正9)年からは、日暮里渡辺町に住んでいた。参考文献:「新潮日本文学アルバム 野上弥生子」 ㈱新潮社
十二時頃私たち − 私と素一と茂吉郎と燿三とその他女中の二人よしとまさは茶の間に集まつてゐた。やがておひるだと話しながら、其処へ、急に地震が起きた。私はふだんから地震は一息の間ぢつと目をつぶつて我まんしてゐればすむものとおもつてゐたので、怖くはないくと子供たちに云ひながらぢつとさしておいた。が、家の震へは中ゝ止まらなかつた。どうもたゞの地震ではないらしくおもへたので、洋館の方が去年の新築で大丈夫だらうといふことで洋館の子供部屋に移つた。しかしまだ震動がやまない。と、地震の時には吃度起るときいてゐた火事のことがおもはれた。もし火事でも出てはこゝは奥まりすぎてるとおもふので、又茶の間に引きかへすと近所では皆外に出たらしいといふので私も一二人の子供を連れ、日暮公園に行く。その間絶えず震動が続くので公園の稲荷前の桜の木が左右に立つてゐるベンチに腰かけてゐた。避難の人ゞが既に大分来てをり、又あとからあとからと集まつて来た。よしとまさは家が気にかゝると云つて残つてゐて、呉座など運ぶ。又ガスも水道も出なくなつたから夜の用意にとてらうそくや食料を運ぶ。私は有りつたけの金をおびの間に入れて遁げたのである。その内に本所浅草の方が火事になつたと云つて、燃えた紙や灰が道灌山を越して落ちて来た。十二階が半分から倒れて下が火になつたとか、下町の方はすべての建物が倒れたとか外出の人々が帰つて来る度に避難者たちの間に怖ろしい新たな報告がもたらされた。茂吉郎は余りおどろいたのと、心配とのために胸を悪くして戻してばかりゐる。高野さんに連れて行つてお薬を貰ふ。此処はそんなことは非常に便利である。又土地柄から云つても、元は山なのだから、この土地が崩壊してしまふやうなことはありえないから、此処にさへゐれば大丈夫だとおもつてゐた。しかし父様はこれをしらないのだとおもふと、明日にも誰かたのんで山の方に知らせ度いとおもつた。夕ごほんに一寸と帰り、又夜中に遁げるやうなことがあつてほならぬとおもつたので、野宿することにして、フトンやカヤを運ばせてねた。絶えず護れる。火事はますます大きくひろがり、夜もその火で明るく灯が要らない位であつた。眠らないつもりでもたえずたえずうとうとしてゐた。丁度夜明け頃におもひがけもなく父様が帰つて来てくれた。その時は本とうにうれしかつた。父様がどうして今帰つて来たか、ほんとうにそれはキセキに近いことであつた。私たちは矢張り運命からめぐまれてゐるのだと云ふ気がする。
私は今度こそ怖ろしいといふものを感じ、見た。而してつくづく人間の無力を知つた。心から自然に対してケンソンな気もちになり、神に祈つた。
大正12年9月大地震の記 大正十二年九月一日「野上弥生子日記」 1984年5月2日第1刷発行 ㈱岩波書店
王子村大字上十条の農家に生まれ王子町の吏員となった高木助一郎(1892~1947)は、吏員と云う立場上から、その日記に震災の模様を事細かに書き残している。
一日休暇を貰ひて昼食を喰ひ語りし時、午前十一時五十八分大地震あり。引き続き第二回あり。震動甚し<皆な驚き叫びて戸外ににげる。浩一寝たる上に帯戸二枚倒れたるも幸に無事なりし。庭の石灯籠皆倒る。幸ひに他に大なる損害なし。 直ちに砲兵工廠其他より逃れ返るもの陸続たり。高木作次郎氏物置の屋根瓦は落つ。高木富蔵氏住宅の屋根瓦全部落つ。震後豊島に火災起る(焼失家屋三十六戸)。予は直ちに役場に出勤。第二学校に於て焚出並に救護所設置に着き同所に出張する
一、終日余震数十回に及ぶ。
一、王子町に於ては下の部即ち榎町、柳町、鎗溝、大字豊島、同堀舟方面倒壊家屋非常に多く無慮三、四千戸に及ぶ見込み。
一、板橋工科学校焼失せり。
一、王子町に於ては直ちに焚出所を左の通り設置し、救護事務を開始す。
王子町役場前。王子第二小学校。王子第一小学校。豊川小学校。堀舟小学校。堀江松五郎氏宅。
一、東京市は倒壊と同時に数十ヶ所より出火したる由にて黒煙朦々たり。
一、午後三時頃より東南の空に当りて怪しき白雲ももくとして恰も地中より涌き出づるが如く中天に揚り、人心洶々として定まらず、海中の噴火なりか流言甚だし。
一、大震と同時に電車汽車等総ての交通機関途絶、汽車は中途に於て線路上に停止したるままなり。
一、電信電話等不通。
一、罹災民は余震甚しき為め屋内に寝ず、道路其他広場に集合、露営恰も露店商店の如し。
一、電灯瓦斯等点火せず皆な真の闇み提灯によりて僅かに明りを探るのみ。
一、夜東京市の空と思はるる限り火災天をこがし物き凄き事限りなし。
一、焚出所に於て徹夜戦々恟々として二日に至る。東京の火災まだ止まず。
「一市井人が日誌で綴った/近代日本自分史[1908〜1947] 九月一日 土曜日 小雨 大地震」高木助一郎著/本間健彦編 街から舎
■巣鴨・真性寺境内にある関東大震災遭難者供養塔

■巣鴨・真性寺境内にある関東大震災遭難者供養塔